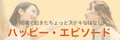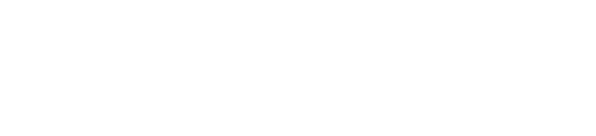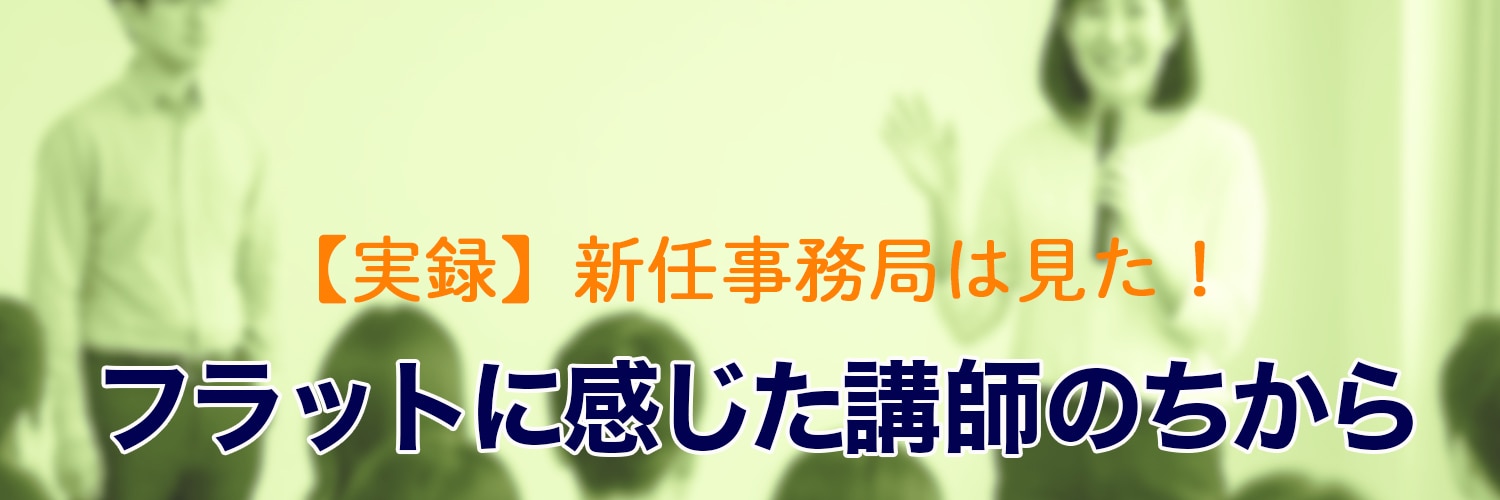
『不器用』だからこそ、人を動かせる 谷屋志郎講師の「現場を元気にする力」
皆様、お久しぶりでございます。このコーナーを執筆させていただいています、ワンスアラウンド株式会社の藤井です。
秋も深まり、朝晩はめっきり冷え込むようになりましたね。
とは書いたものの、今は秋なのでしょうか。
寒くなったと思ったらあったかくなり、そう思ったらすごく寒くなり、もう秋が何なのか分かりません。
天気の駆け引きに翻弄され、地球に恋してしまいそうです。
訳が分からないですよね。すみません。
さて、前回は金谷 舞講師の『現場を元気にする力』についてレポートさせていただきました。
第三回は、販売員歴28年、店長→エリアマネージャー→統括部長を歴任した、谷屋志郎講師のご紹介です。
『不器用』だからこそ、人を動かせる
谷屋志郎講師の「現場を元気にする力」
店長時代に、恩田講師を採用した人でもある谷屋講師は、「とにかく服が好き」という情熱を原動力に、これまで数多くのブランドマネジメントに携わってきました。
講師を務めている現在は、様々な研修を手掛ける中でも、特に得意としているのがSNS研修です。
日々刻々と変化するアルゴリズム(どの投稿が誰に表示されるかを決める仕組み)を、まるで追いかけるように学び続け、その知識を現場に還元しています。
ある受講者のSNSアカウントは、谷屋講師の指導によってフォロワー数百人から数万人へと飛躍的に成長しました。
実は私もセールス時代に谷屋講師からレクチャーを受け、SNSの売上が年間約2億円にまでなった経験があります。
谷屋講師は、販売スタッフから統括部長まで幅広い経験を持ち、現場の悩みを深く理解しています。
そのため、研修では受講者との心の距離感が近く、店頭に立つスタッフの本音に寄り添った指導が特徴です。失敗を隠さず語り、気持ちに正直に向き合う姿勢は、受講者から厚い信頼を集めています。
そんな谷屋講師と一緒にお仕事をさせていただく際、私が谷屋講師から強く感じるのは、「かっこいい泥臭さ」です。
今回は、その泥臭さの中にこそ存在する、谷屋講師の「現場を元気にする」3つのチカラにフォーカスしてお伝えしようと思います。
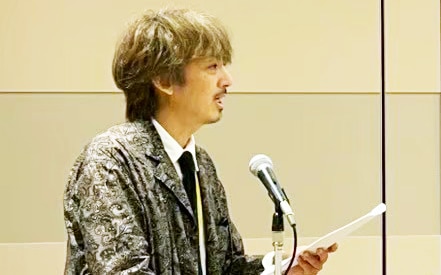
飾らず、等身大で向き合う
【3つの強み】
リアリティに根ざした説得力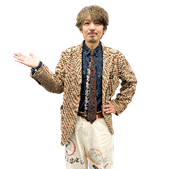
谷屋講師の研修に同行して感じるのは、他の講師とは少し違った独特の説得力です。
それは「カリスマ性」というよりも、現場での試行錯誤の積み重ねが膨大であるがゆえの、地に足の着いた説得力なのです。
ある時、ランチをご一緒させていただいた際、谷屋講師はこうおっしゃっていました。
「俺、不器用だからさ、社長から言われたこととか、目の前のことに必死で食らいついていたら、いつの間にかこうなってたんだよね。」
この言葉を聞いた時、私は谷屋講師の魅力の本質が見えた気がしました。煌びやかな成功体験ではなく、泥臭く必死にもがいた経験の数々。それこそが、現場のリーダーたちの心に深く響く理由なのかもしれません。
実際、講義中には「入社三年目ぐらいは売上がどういった数字で作られるかを知らなかった」「お盆など売上が集中するときにとにかくスタッフを集めたが、指示しきれずにスタッフを持て余してしまい無駄になった。頭ではわかっていても、いざ働いている際にコストの面も意識して売上や利益を考えて動くことが難しかった」といった失敗談を飾らずに語ってくださいます。
こうしたトライアンドエラーからの学びの「質」と「量」こそが、谷屋講師の「地に足の着いた説得力」を作り上げているように感じました。
現場で日々悩むリーダーの皆様には、同じように悩み、失敗を乗り越えてきた谷屋講師の言葉が深く腹落ちできるのかもしれません。
「寄り添い」「気持ち」を伝え「気持ち」に寄り添う。 |
|
そして、谷屋講師の強みは、結果やロジックだけでなく、人の「気持ち」に深くアプローチする力だと感じています。
以前、私がミスをした際に谷屋講師からフィードバックをいただいた時のことですが「俺は今回の件がとても残念だけど、なんでこういった結果になったのかな?」と、ご自身の気持ちを何度も伝えながらフィードバックしてくださいました。
単に失敗の原因追及や影響の説明だけではなく、「残念に思う」という正直な気持ちを伝えてもらったことで、私はより深刻に受け止め、同じ失敗を繰り返さないということが強く心に刻まれました。
これは、結果や理屈以上に「感情」が人の記憶に強く残るということなのかもしれません。
「今後どんな影響があるか」よりも、「目の前にいるこの人を裏切ってしまった」という感情の方が、私たちの行動や記憶に色濃く残るように思います。もちろんネガティブな場面だけでなく、ポジティブな場面でも同じことが言えます。
調査チームの上長も、店長時代に谷屋講師に相談していた際、「絶対に否定することなく、とにかく共感してくれていた。共感の気持ちに救われていた」と言っていました。
共感のフレーズは「うん、うん、そうだよね」というシンプルな言葉ですが、その中で質問を重ねて相手に深く話してもらうという徹底した傾聴姿勢こそが、谷屋講師流の「気持ちへの共感」の真髄なのだと感じました。
皆様も、部下に何度も同じミスを繰り返されて困った経験はありませんか?
谷屋講師のフィードバックを見ていて私が感じたのは、結果や理屈だけでなく「自分がどう感じたか」という気持ちを正直に伝えることが、部下の心に深く刻まれ、失敗を繰り返さない学習につながるのかもしれない、ということです。
「弱みを見せる勇気」が作る心理的安全性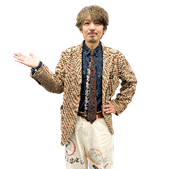
谷屋講師には、自身の豊富な経験をひけらかすことなく、むしろ「俺わかんないから教えてくれない?」と私たち若手にも素直に教えを乞う姿勢があります。もちろん「わからない」で終わり、ではなく「わからないからどうする」までがセットです。
この素直な姿勢が、現場の報連相やチームワークに大きな好循環を生んでいるように感じます。
「人は鏡」という言葉がありますが、谷屋講師のようにオープンで謙虚な方だからこそ、私たちもサポートしたいと思うのはもちろん、こちらからも質問がしやすくなるんです。
私自身、以前は質問されたら「何か答えなければいけない」と思い込み、答えが出せないと黙り込んでしまうことがありました。しかし、谷屋講師が「わからない」と素直に答える姿を見て以来、私自身もその言葉が言いやすくなり、教えを乞うことのハードルが下がったと強く感じています。
これは非常に重要なことかもしれません。
部下が気軽に質問や相談をできる環境があれば、ミスが起きる前に防ぐことができるのではないか、と思うんです。
上司が自ら弱みを見せる勇気を持つことで、部下は「自分の意見を主張しても大丈夫」「わからないことを質問しても恥ずかしくない」と感じられるようになり、問題が大きくなる前に相談が上がってくるようになる。そんな心理的安全性を、谷屋講師の姿勢から感じました。
『本音で向き合う姿勢』が現場を変える
私が感じる谷屋講師の魅力は、現場での幅広い経験に裏打ちされた「失敗を教訓に変える泥臭い説得力」です。そして、経験に基づき「現場の悩みに深く共感する姿勢」と「組織に安心感をもたらす弱みを見せる勇気」を兼ね備えています。
現場を元気に、そして笑顔にするためには、トライアンドエラーを繰り返して成長していくことが不可欠だと思います。
谷屋講師を見ていて私が感じたのは、感情を込めたフィードバックで部下の記憶に深く刻むことと、リーダー自身が弱みを見せる勇気を持つことで心理的安全性を作り、部下が気軽に相談できる環境を整えることの二つが、失敗を成長に変えるサイクルを作る鍵になるのかもしれない、ということです。
まだまだ経験の浅い私が偉そうに語れることではありませんが、谷屋講師の姿を通して、「本音で向き合う姿勢」が現場を変える可能性を感じています。皆様はどのようにお感じになるでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
これからも弊社講師の魅力(拘り)をご紹介してまいります。